プーシキンについて
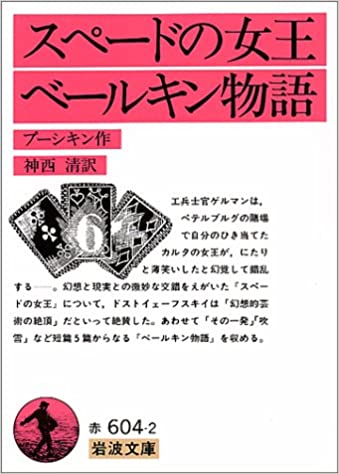
私は学生時代ロシア文学をやってましたが、いわゆるロシア文学黄金期の作家たちが皆「われわれはプーシキンから来た」と言っていたことは有名です。 プーシキンは37才にして決闘で倒れ、ロシア革命以前の反体制派デカブリストの乱に関わったとして流浪生活を送っています。 200年前の人でありながら、ロシアの野蛮と社会主義への傾斜を既に持ち、その後に続く作家たちに多大の影響を与えた作家、プーシキンの魅力はどこにあるのでしょう?
プーシキンの詩
プーシキンは第一に詩人、それも第一級の詩人です。 例えば「若者の墓」。
……かれは消えた
恋と楽しみに育まれたやさしい若者
かれはいまふかい眠りとおだやかな
墓のさむさにつつまれている……
……
あるいは「***に」。
……
わたしの心は過ぎた日々の
あまたの恋につかれている。
けれどもおりふしゆくりなく
天使のようにきよらかな
若い乙女がわたしのまえを
通りすぎ消えてゆくとき
どうしてわたしはひとときの
夢を見ないでいられよう。
彼の詩は青春の詩であるばかりでなく、永遠の若さを保つ詩です。 その詩を読む者は皆、自分の青春を心からの懐かしさをもって思い出さずにはいられません。
プーシキンの長編
彼の詩以外の作品も、この詩的魂から生まれたに違いありません。 なぜなら、彼の小説は短編を除き、何年かの時をかけて完成されています。 計算して書かれたものではなく、湧き上がる興に任せて筆を走らせたに違いないと思えるのです。 典型は「エブゲニー・オネーギン」で、1825年から1832年まで7年をかけて1章ずつ書かれた上に「韻文小説」と銘打たれています。
ニヒリストのオネーギンと夢見がちで純粋なタチアナの話で、男女がお互い相手を必要とする時には相手はあらぬ方を向いているという悲劇を描いています。 タチアナがオネーギンのの手紙をぼろぼろ涙をこぼしながら読みながら、その求愛を断る最後のシーンは感動的です。
プーシキンの長編では「大尉の娘」が一番いいと言われているようですが、どうでしょうか。 この作品はブガチョーフの反乱を題材にした歴史小説です。 新参の軍人ペトルーシャが、文字通り大尉の娘であるマーシャを愛し、反乱に翻弄されながらも結ばれるまでを描きます。 何とプーシキンは最終稿で14章のうちのほとんど1章をカットしています。 彼にはきっと冗長は耐えられなかったのでしょう。 その話運びも、きわめてアップテンポです。 しかし、それでも、その短編に比べれば、はるかに完成度が落ちます。
プーシキンの短編
「スペードの女王」は賭博の話で、勝ったと思った札が開けてみるとスペードのクイーンに変わり、その顔が主人公に微笑みかけるというラストが不気味です。 構成は一分のスキもありません。 しかし、あまりにも有名なので、今は論じないでおきましょう。
私がお薦めしたい作品は「ベールキン物語」。 これは5つの短編からなる短編集で、中でも素晴らしいのが「吹雪」と「その一発」です。 2作とも、めんめんと語られた昔語りが現在に届いた瞬間パッと終わるのですが、その結末の見事さは「あっ」と息を飲む思いです。 この短い語りの中で、この作家は人の生涯の素描をなんと完全にやりとげていることでしょう!
「吹雪」は駆け落ちを約束した二人が運命にもて遊ばれる話ですが、ハッピーエンドに終わります。 というと、最後に結婚するのかと思いきや、結婚が許された後、男は二度とマリヤには会わないといって従軍し、挙げ句は死んでしまうのです。 読者は完全に悲劇を予想するのですが、ここからこの作者は「吹雪」による人ちがいを完全に予想外の結末へとつなげていきます。 その手腕の見事さは類を見ません。
「その一発」はこれとは違い、悲劇です。 そうは言っても、ロシアのトスカ(憂鬱)な気分におおわれたトラジコメディ(悲喜劇)といったほうがいいでしょう。 語り手の青年が出会ったどこか暗い影のある拳銃の名手シルヴィオ、その声望と没落、そしてこつ然とした失踪。 全て劇的で、数年後、語り手が農場主として生活を始めたとき、隣へやってきた伯爵夫妻との邂逅がシルヴィオ失踪の謎を解いてくれるわけです。 ここでも、その鍵は題名の「その一発」にあります。 そこにはシルヴィオの人生が凝縮されているのです。
ロシア文学の歴史と今後
プーシキンは帝政ロシア時代、いわば反体制の作家ではありましたが、まがりなりにも書きたいことは書けていました。 プーシキン後継者であるトルストイ、ドストエフスキーなどを飛ばし、時代は社会主義ロシアへと移ります。 検閲で書きたいことも書けなくなった時代、文学は死んだかもしれません。 革命とともに生きたといわれるゴーリキーにしてもあのロシア文学黄金期に比べれば明らかに小粒。 才能豊かだった詩人のマヤコフスキーはピストル自殺。 ラスプーチンやアイトマートフの作品にしたところで、到底19世紀ロシア文学の華々しさには及びません。
作家たちは「ソラリス」や「ストーカー」といった、反体制をSFの寓喩の中に封じこめた作品を書きます。 いわば、抽象絵画のような謎めいた世界。 そこにはもうプーシキンのようなドラマチックで、わかりやすく、共感できる作品はありません。
先日起きたウクライナへのロシア軍の侵攻は衝撃でした。 プーシキンの活動は主にロシアでなされたとはいえ、ウクライナは彼がかつて住んでいたこともある土地です。 社会主義がロシアの地に住む貧しい民の生活を改善したことは確かかもしれません。 それはデカブリストの乱に共感したプーシキンの志の延長線上で生まれた体制なのかもしれません。 しかし、それは今必要以上に人々の精神を規制し、過去からの亡霊のように、人々の行動の自由を妨げているばかりか、人の命まで奪っています。 一体何のための主義であり、何のための体制なのでしょう?
そもそも、プーシキンの文学はバイロン、シェークスピアといった西欧作家の影響を色濃く受けたロシアの魂が生んだ、ロシアと西欧の融合です。 新しいウクライナの自由な大地に、21世紀のプーシキンが誕生することを期待してやみません。
※冒頭の写真はスペードの女王・ベールキン物語 (岩波文庫)の表紙です。
コメント 記事が気に入ったらいいねしてね!  0
0  146
146
ウクライナ情勢も結局は大国間のエゴの衝突でしかないので、当事国の国民の恐怖を想うと胸が痛みます。文学や音楽などの芸術はそれを阻止はできませんが、少なくとも長い歴史の中で一定の役割を果たしているので、大切にしたいと思います。
今回のウクライナ侵攻には本当にいろんなことを考えさせられます。
プーチンはウクライナ人は歴史的にロシア人と同じ民族だという長い論文を書いて、それにこだわって周囲の反対を押し切って侵攻したという説が結構有力ですが、その理屈でいけばアメリカはイギリスに侵攻し、あるいは多民族国家は分裂につぐ分裂をすることになる気が……まるでナンセンスです。
日本の中に居ると「灯台下暗し」なのですが、今のウクライナだけを見ても日本の戦前・戦中とあまり変わらないわけです。
日本人が歩んだ歴史には一定の意味があると感じています。私は広島人なので今でも無意識的に米国を「敵国」と言ってしまい「同盟国」と訂正されていますが、「共生」という日本的な考え方がこれからますます重要性を増しているような気がします・・・😁
確かにどんどん距離が縮まっていく世界では「共生」が不可欠でしょう。
「大尉の娘」のプガチョーフの反乱ですが(18世紀)、反乱軍の正体はコサックです。ウクライナはコサック発祥の地と言われています。北方ロシアは昔からコサックに手を焼き、それを力で抑えつけてきました(中国とウイグルの関係に似ている?)。ウクライナ人の心の底にはロシア人がまた来やがったという無意識の反発があるかもしれません。
欧米人のリーダーや権力者の基本的な考え方が変わっていないのであれば、ロシア大統領が2発の核兵器をウクライナの地方都市に打ち込むことは十分にありえるのではないでしょうか?😁
しかし、小型の戦術核使用は考えられなくはないですね。チェルノブイリや原発をIAEAの警告を無視して攻撃している国ですから……。
ただ、一旦核を使ったとわかれば今どころではない、永遠にロシアは国際社会から締め出される可能性大です。といって核とわからなければ威嚇効果は小さい。そのあたりを考え、さすがのプーチンも踏み出せないと期待します。
日本人には従いていけませんが、いまだに革命家として織田信長は日本人だけでなく欧米人にも人気があるし、「忠臣蔵」の大石内蔵助と四十七士は町民から拍手喝采され今でも人気があるので、吉良としては毎年年末には打首になり、翌年には火の鳥のごとく新しく蘇る😁
ところで、SFというと、その始まりがポオだったり、ヴェルヌ、ウェルズ、それにコナン・ドイルといますが、誰か好きな作家いますか? 日本だと御三家といわれる小松左京、星新一……。
日本の作家では安部公房ですが、純粋なSF作家ではないので、やはりコミックやアニメ、例えば手塚治虫や宮崎駿などが好きですね。文字よりビジュアル寄りなのかもしれませんが・・・😁
昔の記録を処分していると、結構考えさせられ、また小説のネタも見つかります。いつの間にか私が学んだロシア文学科は大学から消え、かつて修学旅行に生徒を引率した中国へなど奇跡でもなければ行く学校もなくなりました…。
作家が好きというよりSFっぽい作品に絞ると、例えば宮部みゆきの「蒲生邸事件」とか、士郎正宗の「攻殻機動隊」などがありますね。
最近の攻殻機動隊には「1984年」が出てきたり、「大怪獣のあとしまつ」はゴジラ映画のパロディーだったりと、今の若い人にはわからないであろう要素が出てくるとニヤリとしてしまいます😁
考えると、古来、児童文学が描くのは「青い鳥」「銀河鉄道の夜」「オズ」など、大なり小なり異界へ行って現実へ戻る(あるいは非日常から日常)という意味の異界体験だったことに気づきます。とするとこれも広い意味のSFですね。
これらは児童文学ですが、以前から、現代という時代、売れ行きや読者への迎合などなく、純粋に人間を掘り下げ、思いきり理想を追求できるのは児童文学の領域でしかできないんじゃないかと思ってます。
より深い意味では、人が何から始めるかという気質にも関わっているかもしれません。チョコとポテチがあった時、好きなチョコをまず食べるか、好きだから残しておくかという…😅。
小説というのは一般に一人称のナラティブが最強です。ただスリラーでこれをやられると非常に怖い。そこで、三人称で「彼」などと言いながら実質作家が彼になったつもりで書いているという作品も多いですね。「バッテリー」(あさのあつこ)など沢山あります。
私には、純然たる He(She) は私小説作家と言われますが冷静客観志向の志賀直哉、純粋な I は告白体と言われるルソー、He(She) の形をとる I は数えきれないけれど「夜間飛行」のサン=テグジュペリというイメージがあります。ちなみに You は「生れ出づる悩み」の有島武郎ですね。
私の作品はビジュアル(3DCG/VR)なので、どうしても自分の目で見る視点で表現してしまいますが、文学作品ではいろいろな視点で表現できる自由度を感じます。私のような凡人には自由度の低さが逆に有利に働きますが😁
こないだ作った【コメント通知機能】使われてますか?
このページもちょっと重くなってきました。
明日ちょっとした記事を上げるので、コメントはそっちの方へください。
🕍 同ジャンル最新記事(-7件)
2022/03/02
